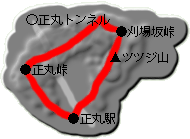西武秩父線・正丸駅がスタート地点
発券機を操作して前払いする
駅の改札脇に登山届があるので忘れずに出そう
ツツジ山への登山道入り口は標識がないので分かりにくい。地図を見て登った先は民家の庭先に入って墓地から車道に上がるものだったので、最初からこの車道を登るべき
三田久保峠
小ツツジ山
小ツツジ山から一旦下って次のピークに登ると、また小都津路山の標識があり、その下に小さく大都津路山と書かれている。ややこしい
ツツジ山山頂(標高879M)
2014年版の昭文社刊『奥武蔵・秩父』の地図ではこの場所は横見山となっており、2015年の吉備人出版『奥武蔵登山詳細図』では刈場坂山となっている
2014年版の昭文社刊『奥武蔵・秩父』の地図ではこの場所は横見山となっており、2015年の吉備人出版『奥武蔵登山詳細図』では刈場坂山となっている
ツツジ山山頂からの眺め
山頂を少し下ると奥武蔵グリーンラインの車道に出る
刈場坂峠。昭和初期、西武鉄道(当時は武蔵野鉄道)が初めて作ったスキー場、奥武蔵スキー場がこの辺りにあった
刈場坂峠からの眺め。堂平山
刈場坂峠の様子。駐車場とトイレあり
刈場坂峠から大野峠方面に向かう
刈場坂峠のかつての繁栄の跡だろうか。別荘地風の廃墟が続いている
牛立久保から虚空蔵峠へ向かう
牛立久保から虚空蔵峠までは緩い下りで一息つける
一旦車道に出て、東屋の建つ虚空蔵峠から再び登山道へと入る
正丸峠までアップダウンが連続する修行区間に突入
登って下るとサッキョ峠
サッキョ峠からの登り。アップダウンの繰り返しは己との戦い
登って下ると旧正丸峠。ここからでも正丸駅に降りられるが予定通り次に進む
旧正丸峠からの登り。心が折れそうになる
登ったところが川越山
次のピークが正丸山
正丸山を降りれば正丸峠。後は降りるだけだ
頭文字Dにも登場する正丸峠に建つ奥村茶屋