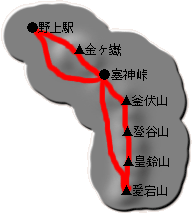秩父鉄道野上駅の日貸し駐車場にクルマを預けて登山開始
金ヶ嶽登山口
金ヶ嶽(標高382M)山頂の春日神社
?? 標柱だ。塞神峠は左とあるが、左に尾根はない。尾根は右である。ここでようやく目指すところが塞神峠ではなく右の葉原峠である事を確信した
!! チェックポイント12。なんのことはない。チェックポイント11からおそらく2分ほどで来られるところを30分も費やしてしまった。よもやよもやである
釜山神社の標柱。もう大丈夫だ
チェックポイント13。ここが植平峠
チェックポイント15。仙元峠
塞神峠に到着。ここからは明瞭な車道歩きだ
釜伏山(標高582M)山頂
釜山神社
釜伏峠
登谷山(とやさん)を蔽うソーラーパネル
山頂とは逆方向の登谷無線中継所に寄り道
登谷山(標高668M)山頂