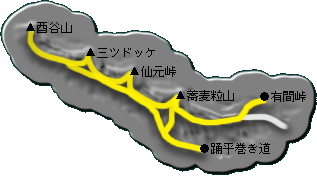全国的に異常気象となった平成26年の夏。連日の雨で有間峠に向かう林道もいたる所で落石していた。引き返そうかとも思ったが、落石をどかして先へ進んだ
予定時刻を1時間30分遅れて登山開始。山慣れから来る驕りが後に遭難の危地を招こうとは、この時知る由もない
有間峠から林道を進む。行く手を遮る鎖がこれ以上の進入を阻んでいるかのようだ
脊梁山脈最初のピーク蕎麦粒山(標高1,473M)
樹齢200年を超えるブナの原生林
一杯水避難小屋。少し手前に一杯水が湧く
三ツドッケ(標高1,576M)山頂。樹木に何枚も取り付けられた標識は天目山となっている
濡れて滑る桟橋。滑り落ちたら自力で這い上がってこられない急斜面が靄の中に消えている
薄暗い長沢背稜を行く
酉谷峠の眼下には酉谷避難小屋