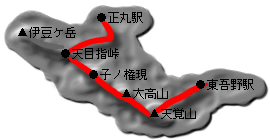正丸駅にクルマを置き、東吾野まで電車で移動
登山道の分岐。左が沢コース、右が尾根コース
天覚山山頂(標高445.5M)
大高山からは、どうでもいい小ピークを迂回できる捲き道が用意されている
車道が登山道を分断している
前坂分岐点。右に降りれば吾野駅、まっすぐ行くと子の権現に至る地図上破線ルート。破線ルートを進む
吾野駅近くにある鉱山の警告看板。尾根ルートはここから立ち入り禁止となり、一旦降ろされる
む〜っ、さすがに破線ルート。篠の藪だ
車道に出て少し登る